検定が出来るまでの30年Vol.8 プロフェッショナルへのプロローグ
入社後、現場配属になってから、半年が過ぎ、やっと一人前に扱われ、毎日が充実した頃であった。私は、宴会部門の仕事をしていたが、暇な時間は、シルバー磨きや宴会場の掃除など、しなければならないことが沢山あった。そんな時、倉庫の掃除をしていて、オーバルのココットで幅が50㎝くらいの器があり、その器を一度に10個ほど割ってしまった。金額にすると1個25,000円ほどするので、その時は料理長に謝罪すのが怖くて、ちょっと大げさだが自殺したい気分だった。覚悟を決めて謝罪に行った。そうすると意外とあっさりしていて、「分かった、今度から気をつけろよ」と言われただけだった。今までの料理長からは想像も出来ない言葉だった。実は、一週間ほど前からアネックスの総支配人に就任したばかりだった。総支配人という立場になって人が変わったように穏やかになった。自分は、新入社員とは言うものの、年齢でいえば25歳であった。このころは、日本一のウエイターを目指していたころだったので、For the customerを徹底的に追及している時期だった。一人前と認められてからは、とにかくお客様の満足することは、何でもやっていこうと思っていた。そんなことで、保守的でモチベーションの低い調理場と毎日のようにもめていた。私は、とにかくお客様の要望を完全な形で実現することを目指していた。そのためには、何とか調理場に協力してもらわないとそれが実現できなかった。それで思いついたのが、調理場の人たちから自分を認めてもらわなければそれが実現できないと思った。そこで、私は、自分で調理人のように料理はできないが、料理とその調理方法、食材の知識では、調理の人の上を行こうと思い、その目標に向けて、勉強することにした。まず、当時の自分の1か月分の給料程する料理の本を8冊購入した。1冊、当時12,000円以上した本であった。大学時代に貯めた貯金を使い一度にまとめて購入した。
日曜日は毎週確実に休みだったので、前日の土曜日は、スーパーの閉店時間に間に合うようになるべく早く帰るようにして、そのレストランの全メニューを作ったのである。一つのメニューが美味しく食べられるようになるまで、何日も要したメニューもあった。もちろん、作り方がどうしてもわからないメニューも沢山あった。そんな時には、いつも親切に指導してくれた調理の方に、休憩時間に聞いてできるようになるまで作り続けた。全メニューをとりあえず形になるまで作り続けたが、半年以上かかってしまった。同時に、有名な料理は、素材と作り方を頭の中に叩き込んだ。その当時に流行っていた料理だけではなく、オーソドックスフレンチもかなり勉強した。調理人と対等に話せるように、フランス語で素材や調理法が説明できるだけのフランス単語も必死で学んだ。とりあえず、フランス語のメニューを見たら、それがどんな料理なのかおおよそわかるようになった。
これで、調理場とは対等に会話ができるようになったころだった。私がこんなだから、調理場には生意気だと私に意地悪する人もいた。その中でも副料理長が一番きつかった。仕事上のことなのにと思いながらも、お客様のサービスに支障が出る時もあったが、それでも崩しようのない縦社会が確立されていたので、何一つ文句すら言うことができなかった。
そんな時に、Vol.7でご紹介した私の中の一番大切な顧客が来店して、「谷藤君、今日はなんか古き良き時代のフランス料理が食べたいな。珍しくたまにはこってり系がいいかな。なんかお勧め料理はあるかな?」と言われたので、私は、頭をフル回転して思いついた料理は、その当時でもすでに古典的な料理になっていたが、そのお客様のリクエストそのものだった。実は、そのお客様は、何十年もの間、長期海外赴任や海外出張に頻繁に行っており料理やワインにめちゃめちゃ詳しく、東北出身の田舎ものなんかでは全然ないのだ。その思いついた料理とは「ソール・ボン・ファン」という料理で、当然メニューにはない料理だ。いよいよ対決の時だと覚悟を決めた。私の大切なお客様のウォンツを満たすためなので何のためらいもなかった。
通し伝票に記入して、調理場にもっていったら、デシャップが副料理長だった。オーダーを読み上げた瞬間、「おいっ、お前、ちょっと待て」と言われ、いよいよ修羅場を迎えようとしていた。「お前、そのメニューはなんだ。メニューにないだろう。」と睨まれたので、私は「メニューにないと作れないんですか。私は、このレストランは一流だと思っていました。本日のおすすめにソールがあることも確認済みですので、素材があるのに作ってもらえないのですか?これは、上顧客の○○様のリクエストです。」と挑発的な言い方をしたので、「なんで、メニューにないものを受けるんだ。ふざけるなっ。」と右手に牛刀を持ちながら怒鳴りまくられた。ちょうどそこに、総支配人兼総料理長が来て「お前ら、なにやってんだ。谷藤どうしたんだ。」と言われたので、「メニューにないオーダーを取ってきたら怒られました。」というと「何とってきたんだ。」と言われたので「ソール・ボン・ファンです。」というと、「おお、懐かしい料理だな。誰が頼んだんだ。」と言われたので、「○○の○○様です。」と答えると、総料理長は顔色が変わり、副料理長に向かって「お前は、そのお客が頼んだことを知ってたのか?」と怒鳴るように言うと、副料理長が「はい」と答えると、総料理長は、烈火のごとく「このバカヤロー、○○さんがどういう人かお前も知ってるだろう。お前はもういい、俺が作る。」といって、総料理長がその料理を作り始めたのだ。「谷藤、悪いな、俺がこれから作るからよ」といわれ、私はすごく恐縮してしまった。仕事は、勝ち負けではないと思うが、その時私は調理場に料理で勝ったと思った。後である調理の方が、こっそり教えてくれたのだが、副料理長は、どうもソール・ボン・ファンという料理の作り方を詳しく知らなかったらしい。
この日以来、調理場に対して凄く仕事がしやすくなった。また、総支配人兼総料理長の私に対する態度が随分変わったように感じた。
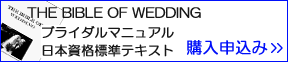


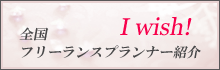



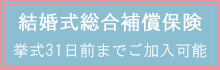
コメント